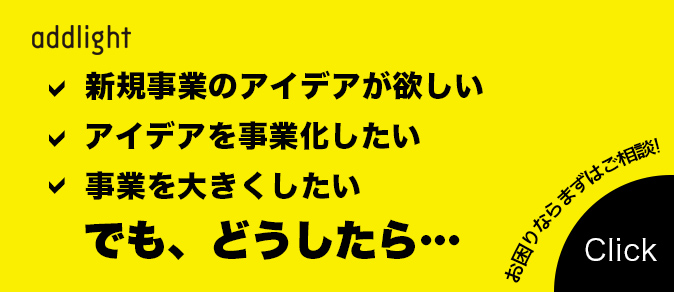2月17日、大阪府主導のアクセラレータープログラム「スタートアップ・イニシャルプログラムOSAKA」によるオープンイベント「中堅企業×スタートアップ 効果的なオープンイノベーションの実践とノウハウ」をオンラインにて開催。ゲストにOS株式会社経営企画部課長・起塚氏、株式会社イースト事業創造部マネージャー・下城氏、原田産業株式会社から鈴木氏、佃氏、加藤氏をお招きし、中堅企業としてオープンイノベーションを実施した経験をお話しいただいた。
スタートアップ・イニシャルプログラムOSAKAとは?
大阪府では、関係機関一丸となってオール大阪によるグローバルなスタートアップエコシステムの構築に取り組んでいる。その一環として、昨年度からスタートアップの成長を支援するため、「スタートアップ・イニシャルプログラムOSAKA(以下、SIO)」を開始した。SIOでは、スタートアップを対象に研修講座やアクセラレータープログラムを実施しており、既存企業(オープンイノベーションパートナー)との連携・協業も促進している。弊社アドライトは株式会社MJEとSIO共同体として本事業の企画運営を務めた。
オープンイノベーションにおける中堅企業の強み
はじめに、弊社代表取締役・木村より、オープンイノベーションに中堅企業が参加する強みに触れた。中堅企業は規模が大きすぎないためスピード感があり、スタートアップとの文化の違いでの戸惑いは少ないという。またファミリービジネスも多く、若手経営者への代替わりのタイミング等で経営方針の大幅な見直しが可能なため、新規事業創出への挑戦の機会につながることを示唆。
中堅企業に限ったことではないが、コロナ禍で経営業態の適応が求められる中、協業は効果的な手段である。今回登壇いただいた3社の事例からも中堅企業がオープンイノベーションに挑戦すべき具体的なポイントが明らかになることを期待していると述べた。
新規事業に興味を持っていた潜在的な社内人材の発見
株式会社イーストは主にショッピングセンター向けにシステム提供や人材派遣を行っている。事業創造部 マネージャー・下城氏は、入社後18年間エンジニアとして働いていたが、3年前新規事業に取り組み始めた。
2020年本プログラム(スタートアップ・イニシャルプログラムOSAKA)への参加をきっかけに、先端テクノロジーを駆使したシステム開発を行っている株式会社アクショムと協業し、商業施設向けAIインフォメーションbootiaを開発。
コロナ禍で非接触化が求められ、提供するサービスのDX化を目指したかったが、自前の技術だけでは難しいため、アクショムのAIやDXに関する技術を必要としていた。bootiaの開発までイースト側が商品企画や顧客の需要調査を担当し、アクショム側がシステム内の技術を主に担当したという。
驚くべきは、協業から顧客への導入までに約半年でこぎつけたスピード感である。ほとんどがリモートでのやり取りとなったが、その分ミーティングのハードルが下がり、密な連携がとれたという。

下城氏は新規事業に取り組んだ3年間を振り返り、bootia開発を成功させた3つの要因を挙げた。1つ目は、社員に数多くの機会に挑戦させた会社の「覚悟」。はじめの2年間は思うような成果を出せなかったが、それでも次の挑戦を会社が認めてくれたからこそbootia開発が成功したという。2つ目は、オープンイノベーション支援企業や支援プログラムによる講座、書籍、外部メンターから、社内起業・協業の方法を「学習」できた点。3つ目は「同じ未来を目指せるか」という点だ。スタートアップと自社の方向性が一致しない場合には協業自体が失敗することが多く、早い段階での方向性の一致が鍵であった。
オープンイノベーションを経て、成果物だけでなく社内の変化が起きて始めているという。新規事業に興味を持つ社員がしっかりと現れるようになったというのだ。それまではやり方が分からず行動に移せていなかったケースが多く、会社も社員の意欲を把握できていなかった。ところが自身を中心に完成したbootiaをきっかけに、興味を示す社員の存在が明確となり、彼らを巻き込んだ今後の展開を期待しているとのことだ。
受動的な姿勢を見直し、先を見据えた新しい価値の提供を達成するツールとしての協業
OS株式会社はエンタメサービス事業、不動産業を中心に空間を生かしてサービスを提供する関西地区に根差した企業である。
経営企画部課長・起塚氏によると、「地域に暮らす人々の幸せや豊かな生活文化と未来づくり」と企業理念にあるように、時代に即した先を見据えた新しい価値の提供を達成したいというビジョンから、ハコモノ産業にありがちな「待ちの姿勢」を改め、協業に取り組むことを決めたという。
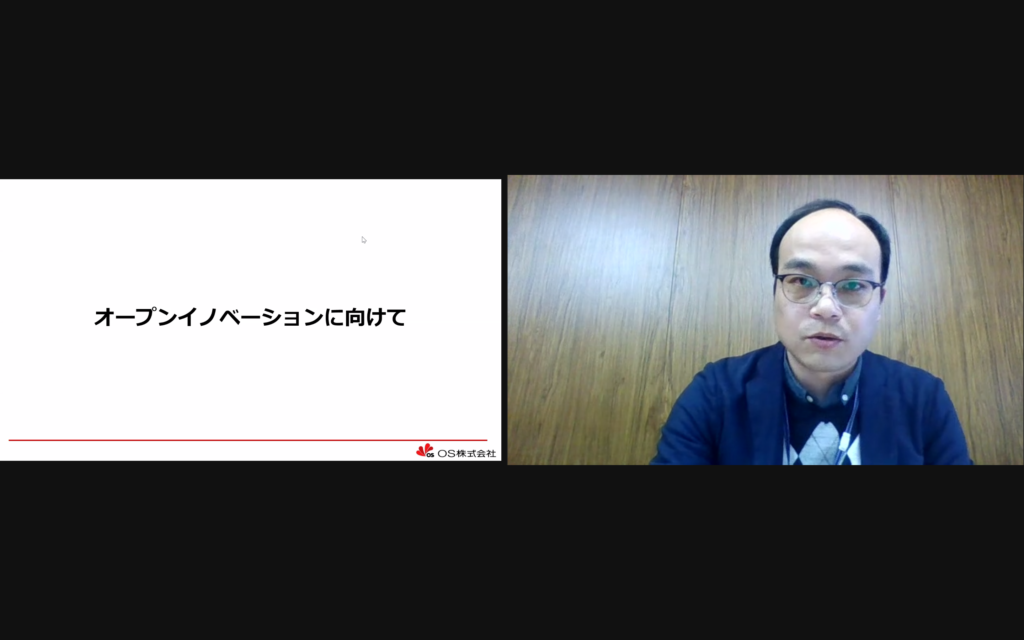
実際に、オープンイノベーションでは従来の自前主義の転換を徹底し、2つの実例を挙げた。株式会社スペースエンジンによるスペースと商品メーカーのマッチングシステム導入だ。普段は上映していないオリジナル作品や地域と結びつきの強い作品を上映することが可能になり、他館との差別化やニッチな作品のファン層の取り込みができたという。
もう一つは、スペースのデザインを強みに持つ株式会社Replaceとの協業だ。屋台形態の飲食企業とOSが保有する不動産の有休スペースを組み合わせ、賑わいのあるスペースを作った。本来の活用法にとらわれない新たな役割を持つスペースを作りだし、企業理念の達成へ近づいている。
現在取り組んでいる協業は、実証実験の段階まで来ているが、「これからの2歩目、3歩目の踏み出し方が重要です」と、気を抜かずに実装へと向かう頼もしい言葉で締めくくられた。
従来の物売りから脱却するためのオープンイノベーション
原田産業株式会社は中堅老舗の総合商社。B2Bのネットワークに強く、ニッチ事業を見つけることに主眼を置いてきた。一方、モノによって課題を解決してきた点が弱みでもあると、Business Co-Creation Team General Manager・鈴木氏は語る。従来の物売りから脱却し、デジタル化、サービス化を進めるには、外部のアイデアや技術の必要性を感じ、オープンイノベーションに取り組み始めたという。

昨年1年間、自社ブランドで立ち上げたアクセラレータープログラムを実施した。既存領域では実際の協業を、新規領域では領域内の情報収集や参入機会の検討を、また何よりもスタートアップとの協業の感覚を掴んでいこうという目標のもと開始した。結果、多様な領域から国内外167社応募があり、9社採択したという。イーストやOS同様、ほぼ全てがオンラインでの活動となったが、うち4社との協業の継続が決定した。他の5社とも様々な点を工夫しつつ、今後の協業を前向きに検討しているという。
オープンイノベーションを通して得られたこととして以下を挙げた。
- 新規市場の情報や新規市場に進出するパートナー候補
- SaaSなどの新しい概念
- オープンイノベーションへの理解、深く考える機会
- 社内への浸透(ゆっくり)
- 新しいネットワーク(行政、ベンチャー、他のアクセラレータープログラム、他の事業会社との新事業担当者)
- 既存市場の課題
- チームでの新ビジネス研究の機会
ゆっくりではあるが、少しずつ社内外の変化を感じているからこそ、2期目への構想も具体的だ。「今後は他の事業会社との横の連携を新しく作ったり、地元の起業経験者からの経験談を積極的に取り込んだり、企業志向の強い学生を巻き込んだりしていきたいです」と熱い思いで語った。
協業相手に求めること
後半は3社がパネラー、弊社木村がモデレートのもとパネルディスカッションを実施。オープンイノベーションに対する各企業のスタイルが見えてきた。
オープンイノベーションに挑戦したきっかけを聞かれると、「新規事業の芽が出ず苦悩している中、アドライト木村さんのオープンイノベーションセミナーに参加し、そこでお会いした大阪府の方からSIOの紹介を受けたことがきっかけ」(イースト 下城氏)、「映画業界という成熟した分野での成長戦略を検討するも、自前では限界があると感じたため」(OS 起塚氏)、「ファミリー事業の代替わりでの気づきという機会によることでした。モノ100%で経営してきたことや、自社内の事業毎の縦割りのシステムに社長が危機感を持っていたことがきっかけ」(原田産業 佃氏)と三者三様だった。
スタートアップの選定も各社で異なった。
「自社が求めているものと相手の強みの技術面での合致に加え、相手側の思いや人間的な相性も重要です。新規事業立ち上げの中で辛い場面を一緒に乗り越える仲間になるので、見逃せない観点でした」(イースト 下城氏)、「自社の既存事業を軸とした親和性を重視しました。その上で、自社のメリットはもちろん、自社の限られた資産を他社がメリットと感じるかどうかも大切にしました」(OS 起塚氏)、「自社にないサービス化、SaaSのノウハウを持っている企業を基準に選んだが、相手チームとの人間的な相性も重要」(原田産業 加藤氏)。
原田産業はさらに自社のアクセラレータプログラムにおいて、書類選考後、30分から1時間のゆっくりとした面接を各候補企業と行ったという。サポート企業等の第三者も入れて客観的な視点も取り入れつつ、協業先の目指す方向やチームの雰囲気を確認できたという。
オープンイノベーションのよりよい進め方
では実際、どのようにスタートアップと協業を進めたのだろうか。イースト・下城氏は、アクショムとの協業時、社内の会議にかける前から頻繁に話し合いを重ね、プロトタイプも実際に用意してもらうなどして社内へこまめに進捗報告。その結果、稟議にかける以前にスタートアップ側の実力を社内に浸透させることができ、上層部は協業を快諾。その後6ヶ月間で成果物を顧客に届けるというスピード感につながったという。
「オープンイノベーションの可能性を示すことができ、社員にも変化が見られてきましたが、全体への波及にはまだまだ時間がかかります」と下城氏。今後事業部の設置等体制を整えることで、さらに大きなムーブメントになっていくことを期待しているとした。
OS 起塚氏は自社の課題感をスタートアップに認識してもらい、その課題に対して互いが提供できることを共有するところから開始。もちろんそれでスムーズに進む場合もあれば、両者できる範囲が重なり合わず見送る場合も。社内にも自社の課題やビジョンを明確にし、オープンイノベーションが有効な手段であることを示して社内承認を進めていったという。
最終的な担当部署の理解・協力を得るまで至っていない部分は課題としつつ、「企業が生き残るうえで新しいことに取り組むことの意義や重要性を社内に発信することで、社内整備の面や社長からの呼びかけで少しずつ変わっている面もあります」とコメント。工夫次第で大手企業とも繋がることができ、ニーズが自社にあることを認識することができたことで、自己肯定感が上がったと感じているという。
原田産業 佃氏は、スタートアップを従来の取引先としてではなく、「一緒に考え、力を併せて共創していくパートナーとして認識」というマインドセットの共有を社内へ徹底したという。また9つのプロジェクトを同時に進めていたため、担当者同士で進捗状況を共有。フィジカルなミーティングができない分、多様なメンバー構成でのミーティングも設けたことでスタートアップ同士での交流が生まれたり等も。
「スタートアップと日々悩みながら地道に取り組んでいる中、担当者達は事業の新しい進め方や感覚を掴めたように思います」と加藤氏。これまでの事業開発や事業投資のやり方だけではなく、様々なステークホルダーと一緒に事業を作り上げていくというやり方がが経営陣にも伝わり、社内にもじわじわと根付いていると感じているという。

イベントの最後には、参加者、ゲストスピーカー、大阪府、MJE、アドライトによる名刺交換会がブレイクアウトルームに分かれて実施された。中堅企業だからこそのスピード感や、オープンイノベーションによる社内での少しずつの変化が、実際の経験談により強く示された。当イベントをきっかけに、より多くの中堅企業がオープンイノベーションへの挑戦を前向きに検討するようになり、スタートアップもまた中堅企業との協業の魅力に気づいていただけたのではないだろうか。