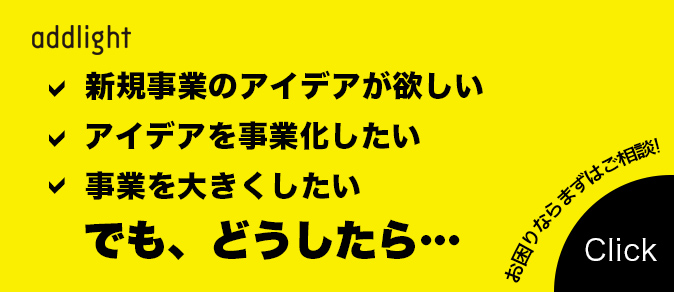新日本製鐵(現・日本製鉄)の製鉄業におけるIT活用を源流として、1980年代に発足した大手ITソリューションベンダーである日鉄ソリューションズ株式会社(以下、日鉄ソリューションズまたはNSSOL)。
※NSSOL、NS Solutions、NS(ロゴ)は、日鉄ソリューションズ株式会社の登録商標です。
日鉄ソリューションズでは、NSSOL2030ビジョンである「Social Value Producer with Digital」を方針に掲げ、新たなビジネスモデルへの転換と新領域への積極的な進出を図っている。アドライトは同社に対し、より大きな視点・視座で社会全体や業種横断の課題解決を行う「ソリューション企画人材」の育成を支援。アドライトが新規事業開発支援で培ったノウハウに、有識者の知見を融合した実践レベルでの講義やワークショップを提供し、ビジネスプランの策定までをサポートした。
今回、同社で本プロジェクトを担当したITサービス&エンジニアリング事業本部 ソリューション企画推進部 専門部長 石田 真治氏とDX&イノベーションセンター エキスパートの川勝 淳郎氏に、プロジェクトの背景や取り組みについてお話を伺った。
会社紹介:日鉄ソリューションズ株式会社
日鉄ソリューションズ株式会社では「創造・信頼・成長」という理念のもと、システムコンサルティング、システム構築、ITインフラ構築、クラウドサービス、AIソリューションなど幅広い分野のITサービスを提供。
2030年のビジョン達成のために新規事業創出人材の育成が課題に
――お二人の所属する部署と役割について教えてください
石田氏:私はITサービス&エンジニアリング事業本部のソリューション企画推進部で新規事業の立ち上げ全般を担当する部長を務めています。当事業本部は会社の売上約3000億円の中でも最大を占める本部で、当事業本部の新規事業を継続的に立ち上げていくことが私の主なミッションです。部内には約30名弱がおり、彼らが新規事業を推進しやすい環境を作ること(フレームワーク作成や人材育成など)と、個別の企画テーマをドライブすることを主な業務としています。
川勝氏:私はデジタルソリューション&コンサルティング本部のDXイノベーションセンター ビジネスイノベーション&コンサルティング部に所属しています。主にソシキノミライというサービスの推進に携わっており、企業の文化醸成支援や新規事業の立ち上げ支援を担当しています。
――プロジェクトに至る課題・きっかけを教えてください。

石田氏:私の所属部門および私自身のミッションとして、ITサービス&ソリューション事業本部全体のソリューション企画人材を育成していかなければならないという責務があります。
今回お願いしたソリューション企画人材育成研修については、どのような人材をターゲットにし、どのようなコンセプトの研修を実施するかを、社内で徹底的に検討し、資料としてまとめました。その資料を元に、研修を実施できる会社を探し、アドライトをはじめ何社かにお声がけしたのがきっかけになります。
メンタリングの手厚さとコストバランスが決め手
――取り組み始めた時期と外部依頼を考えた狙いは何ですか?アドライトを知ったきっかけについても教えてください。
石田氏:研修の必要性自体は2024年の4月頃に話題になり、本格的にコンセプトを具体化したのは4~6月頃でした。私は過去に新規事業やイノベーションの研修を弊社のお客様へ提供した経験があり、その大変さを熟知していたため、こういった研修の経験やノウハウを豊富に持っている外部に依頼することを、初めから決めていました。
そこで、新規事業関連でお付き合いのあった会社を中心に3社ほど候補に挙げました。アドライトは以前に木村社長のプレゼンテーションをイベントで聞いたことがあり、何度かお話をさせていただく中で、いつか一緒に仕事をしたいと考えていました。何度かお声がけしていましたが、今回ようやくご一緒させて頂くことができました。
――選定方法や評価ポイントを教えてください。
石田氏:今回の研修はかなり難易度の高い内容だったため、慎重に選定を行いました。Day1からDay10までの講義が行われる中で、講師のペースではなく参加者のペースに合わせたケアが必要だと考えていました。そこで、講義の合間に1時間ずつメンタリングの時間を設けることを想定していました。3社とも「このタイプの研修にはメンタリングが絶対に必要」と認識していましたが、それによって純粋にコスト増になるため、コストパフォーマンスのバランスが難しいプロジェクトだと思っていました。
私自身もお客様向け研修で見積をしたことがあるプロジェクトだったのですが、アドライトは他社と比較してコストパフォーマンスが高く、弊社内の選定議論の中で「見積の計算間違いではないか」という冗談も出ました(笑)「メンタリングが最も手厚い割に価格がリーズナブル」という点が決め手となり、アドライトを選びました。
川勝氏:私も石田が話した通り、メンタリング、いわゆる1対1でのサポートの手厚さが最も評価できるポイントだったと思います。アドライトの提案は、当社の企画フレームワークに合わせていただけただけでなく、グループごとのサポートも非常に手厚く、安心感がありました。事務局としては、研修参加者への研修後のサポートが十分に行えるか心配だったのですが、その点アドライトは最も手厚いフォローを提案してくださり、それが最終的な決め手になりました。
「新規事業開発を加速させるための研修」というコンセプト設計
――プロジェクトの内容について教えてください。参加人数や期間はどのようなものでしたか?
石田氏:参加者は16名4チームで、期間は8月末から1月初めまでの約5ヶ月間でした。当初はDay10(10回)の予定でしたが、1チームだけ他の3チームより検討が進んでいない状態でのスタートだったため、アドライトから特別に冒頭2回追加のセッションを提案していただき、最終的には12回の講義となりました。このあたりも、他社と比較して柔軟な提案力でした。
――参加者はどのように募集されたのでしょうか?
石田氏:一般的な研修では、カリキュラムの中でアイデアを出し合って最終発表会をするだけで、研修が終わればそのアイデアも忘れられてしまうことが多いのですが、弊社では最初から、研修終了後も企画が継続することに強いコダワリがありました。
そのために、私たちは「研修がなくても元々実施予定だったソリューション企画テーマを研修へ投入し、そこへアサインされる予定だった企画リーダーを研修に参加させ、その下へ育成対象メンバーを付けてチームビルディングする」というコンセプトにしました。これにより、研修終了後も企画が継続され、本気の企画テーマに参加することで学習効果が高まると考えたのです。
この方針で社内の5人の事業部長全員を回り、本気のテーマと人材を出してもらうよう説得しました。「研修がなくてもやるつもりだった企画が、研修参加でより進みが良くなる」という説明を繰り返し、約1.5ヶ月かけて合意を得ました。各事業部長には1時間程度の会議を行い、必要に応じて候補者にも直接説明しました。このように、「プロジェクトを進めるための研修」として設計したことで、各部門の承諾も得られ、実務に直結した内容となりました。
――アドライトのプログラム進行はどうでしたか?
川勝氏:オンラインで開催する際のシステムの問題や講師のスケジュール調整などの問題も多少ありましたが、全体的には非常に進めやすかったですし、全体的にスムーズでした。
特に、期間中にメンタリングを間に挟んでいただけたことが非常に大きかったです。最後のアンケートでも、メンターへの感謝の言葉が参加者から多く寄せられていました。

研修プログラムは参加者からも高い評価
――講義内容については参加者や運営局側から見てどのような評価でしょうか?
川勝氏:特にバリュープロポジションの作成に関しては非常に反響が大きかったです。「かなり難しい」という感想がある反面、「全体を見る大切さを知りました」といった前向きな声も多く聞かれました。
石田氏:講義内容は狙い通りのものでした。私たちが期待していたことを、メンタリングも含めて実施していただきました。「もう少しここをこうしてほしい」というような大きな改善点は思い当たりません。プログラム進行中の調整については、アドライトと密に連絡を取りながら進めることができました。
例えば、グループによって進捗に差があった場合に、そのまま進めるか一旦立ち止まるかといった判断もすり合わせながら行いました。講義は予定通り進めながらも、必要に応じてフォローアップを追加するなど、柔軟に対応いただきました。
川勝氏:新規事業立ち上げ支援の経験がある私から見ても、オーソドックスでありながら網羅的、学術的でありながら実践的なカリキュラムを一から作り上げることは大変なことなので、その点は高く評価しています。また、講師の方々のキャラクターは様々でしたが、講師が切り替わっても参加者が混乱することなくスムーズに進行できたのは良かったと思います。
石田氏:講師が3人リレー形式だったにもかかわらず、非常にスムーズだったと感じます。例えば、インタビューという宿題を出した講師と、その宿題結果を受け取る講師が切り替わってしまった場合などに、つなぎの部分がうまく引き継がれない不安などありましたが、アドライト事務局の精力的な裏側での調整のおかげでスムーズに進行できたのだと思います。
――特に印象的だった講義はありますか?
川勝氏:ソリューション部門の参加者の多くは事業計画の数字詰めをあまり経験していなかったので、その点は新たな学びになりました。また、営業担当者は普段から数字の詰め作業をよく行いますが、今回参加者の多くは営業畑ではない方々だったため、「数字の積み上げ方の考え方がこういうものなのか」というフィードバックがありました。
石田氏: 個人的に最も面白かったのは生成AIを活用したセッションでした。普段はAIに単純な作業を頼んだりするだけですが、今回はアイデアを生成させ、さらにそのアイデアを評価させるという活用法を学べました。きちんと考え抜いてプロンプトを組むというアプローチは意外性があり印象的でした。
――実施した研修の成果についてお聞かせください。
石田氏:成果について定量的に測ることは難しいですが、研修に参加頂いた4つのチームのうち3チームが研修後も企画を継続する見込みとなりました。継続しない1チームも別の企画が急に立ち上がったために継続できなくなっただけで、本研修成果の評価自体は高かったです。投入したテーマが、事業部長から見て継続するに足る状態に仕上がって戻ってきたという点では、非常に高い評価を得ています。
個人の成長については、参加者によってソリューション企画への向き不向きはあるものの、研修を通してそれぞれ確かに成長しました。特に、素養としてソリューション企画へ向いていたが経験が不足していた人材が、バリュープロポジションキャンバスやビジネスモデルキャンバス、ペルソナ作成、インタビュー手法など、これまで経験したことのなかった知識や経験を得ることができました。そういった、素養があった人に知識と経験を与えると成長するという、典型的なロールモデルを作ることができました。
研修を通して特に大きかったのは、講義で得た知識と実際の状況を埋めるメンターの役割です。講義のDayとDayの間に必ずメンタリングがあり、そこでメンターが「講師はこう言っていましたが、あなた方のチームやビジネスの状況を聞くとこうした方がいいですよ」というアドバイスをくれたことで、実践的な経験につながりました。
川勝氏:定量的には、研修終了後に無記名の参加者アンケートから算出したNPSが驚きでした。こういった研修では、NPSがプラスになること自体が非常に珍しいものですが、今回の研修では、「次回開催時に他社員へ参加を勧めたいか」という設問でのNPSが13.3へ達し、異例の高評価が印象的でした。
研修が1月に終わったばかりなので、本業への波及効果についてはまだ観測できていませんが、実務面では、例えば、参加者がインタビューとヒアリングの違いを理解して企画を進められるようになった光景などを見ると、成果を実感します。参加者の多くは、既存事業の延長線上で、お客様から答えを引き出すヒアリングを得意としていました。しかし今回は自分たちで仮説を持ってそれを検証するというアプローチで、より効果的な企画推進をできるようになりました。
――事業部からの評価はいかがでしたか?
石田氏:当本部の幹部や事業部長からの評価も高く、特に「研修という枠組みの中で強制的に進捗する効果」を喜んでいました。通常の企画活動では状況に応じて企画の進捗が遅れることも珍しくないですが、今回は各チームの状況へある程度は合わせつつも、全体としては研修カリキュラムで進んでいくので、参加者もガンガン進まざるを得なかったことが評価されました。
プロジェクト終了後の展望
――研修終了後、事業化に向けてどのように進めていく予定ですか?
石田氏:4つのプロジェクトのうち3つが継続することになりましたが、それぞれ進め方は異なります。例えば、最先端技術を絡めたような企画は、技術そのものがまだ十分な価値提供レベルに達していないため、1年間技術をウォッチし続ける形になります。具体的なニーズの仮説を立てることや、テストユーザーを見つけることすら難しい可能性があります。仮にコンセプトを固めても、それを検証できるレベルの技術がまだ世の中に出ていません。そのため、技術ウォッチと並行して1年間で20〜30社ほどニーズ調査を行っていく予定です。
残りの2つのプロジェクトについては、4月からどのように進めていくか現在所属の事業部長と協議中です。

――これからの会社や個人としてのビジョンについても教えてください。
石田氏:弊社は2030年ビジョンを掲げており、私が所属するITサービス事業本部は売上規模が最も大きい部門です。2030年ビジョンの中で、我々の部門は「売上を倍にして、利益率も倍にする」(利益額では4倍)という大きな目標を課せられています。
既存事業だけでこの目標を達成するのは困難なため、新規事業での成長が不可欠になっています。今回の研修プログラムで育成された人材が、まさにその新規事業を担う中核メンバーとなることが期待されています。
川勝氏:私は企業文化変革の支援という形で、様々な企業をサポートする活動をさらに拡大していく予定です。新規事業に取り組みたいと考えている社内外の組織は多いと思います。
本を読んだり話を聞いたりするだけでなく、今回のようなカリキュラムを通して実際に体験することが重要です。このような「体験を通した学び」を多くの会社に広めていければと思っています。そのような機会があれば、ぜひアドライトにもご協力いただきたいと考えています。
オープンイノベーションや事業立ち上げ、社内起業家育成ならアドライトへ!
事業共創プログラム「SUITz(スーツ)」では、今回ご紹介したような企業を引き合わせて事業共創を行っていきます。ぜひご紹介した企業や本プログラムに興味を持たれた方は弊社アドライトまでご連絡をください。